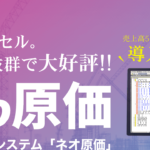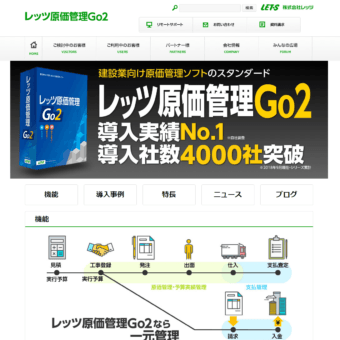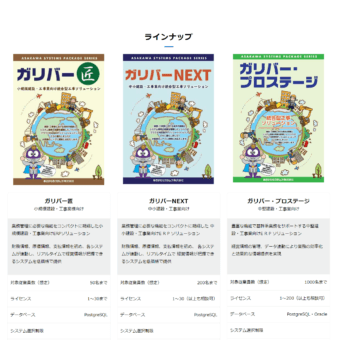原価分析の方法とは?経営判断に使える数字の見方をわかりやすく解説

売上や利益の数字を見ても「なぜ利益が思うように出ていないのか」がわからない場合があります。そうしたときに役立つのが、原価分析です。どこでコストが増えているのか、何を改善すべきかを数字から読み取ることができれば、経営の見直しや業務改善にもつながります。この記事では、原価分析の目的や種類、活用方法をやさしく解説します。
原価分析とは?まずは基本的な考え方から押さえよう
原価分析とは、商品やサービスを提供するうえでかかるコスト(原価)の構造を調べ、数字の背景にある課題や改善点を探る手法のことです。ただ単に原価を計算するだけでなく「コストがどう発生しているのか」「予算との差はなぜ生まれたのか」などを把握することで、経営の意思決定を支える大きな材料になります。
原価分析はなぜ必要なのか
原価分析の目的は、経営のムダや改善ポイントを「数字で発見する」ことです。売上があっても利益が伸びない、同じ商品を扱っているのに部門ごとに利益率が違うといった問題の原因を探るのに役立ちます。
とくに製造業や飲食業など、コスト構造が複雑な業種では、原価の内訳を細かく分析しないと、改善の糸口が見えてきません。
「見える化」で現場とのギャップを埋める
経営層と現場との間で意見が食い違う原因のひとつに、数字の見え方の違いがあります。たとえば「現場ではコストを抑えている」と言っていても、実際には材料ロスが多く、原価が増えていることがあります。
原価分析を通して数字を「見える化」すれば、感覚ではなく事実に基づいて話し合えるようになり、共通認識を持って改善に取り組むことが可能です。
分析の入り口は「予実差」
原価分析の基本は、予算と実績の差を見ることです。「予算では100万円で済むはずだった工程が実際には120万円かかっていた」というような差を洗い出し、その理由を突き止めます。
予算オーバーの背景には、外注費の増加や納期の遅れ、計画ミスなど、さまざまな原因が隠れています。こうした「原価差異」の分析を丁寧に行うことが、根本的な改善策を考える第一歩になります。
どんな業種でも使える手法
原価分析は製造業だけのものと思われがちですが、小売業やサービス業にも応用できます。たとえば小売業では、仕入れ価格の変動や在庫の回転率が利益に大きく影響します。
サービス業では、人件費や外注コストの変化を捉えることが重要です。業種ごとの視点で原価を見つめ直すことが、継続的な利益の確保につながります。
コスト構造を分解して考える
効果的な原価分析を行うには、コストを分類して見ていくことが大切です。たとえば、直接材料費、直接労務費、製造間接費などに分けて、それぞれの増減を比較します。
どこに偏りがあるのか、どの部分が変動しやすいのかを把握すれば、より精度の高い判断が可能になります。
現場の協力も欠かせない
数字だけを見ていても、実際に何が起きているのかはわかりません。たとえば原価が上がっている理由が、工程の見直しなのか、外注業者の価格変更なのかを判断するには、現場の声を聞く必要があります。
現場と管理部門が連携し、リアルな情報を共有することが、正確な分析と実効性のある対策につながります。
原価分析に使える代表的な手法を知ろう
原価分析には複数の手法があります。それぞれに特徴があり、目的や業務内容に合わせて使い分けることが重要です。ここでは、企業でよく使われる代表的な3つの分析方法について紹介します。
原価差異分析でズレを発見する
原価差異分析は、もっとも基本的な原価分析のひとつです。これは、あらかじめ立てた予算と、実際にかかった原価の差を比較し、その原因を探るという手法です。
たとえば「予定より人件費が多くかかっている」「仕入れ価格が予想より高かった」といった情報を細かく分類することで、ムダを発見しやすくなります。原価差異には、材料費差異、労務費差異、作業効率差異などさまざまな分類があります。
これらを正しく把握することで、数字のズレがなぜ起こったのかを深掘り可能です。差異を放置せず定期的にチェックしていくことが、利益の安定につながります。
ABC(活動基準原価計算)で実態に近づく
ABCとは「Activity Based Costing」の略で、日本語では「活動基準原価計算」と呼ばれます。これは、商品の製造やサービス提供にかかる活動そのものに着目し、それぞれの活動がどれだけコストを生み出しているかを計算する方法です。
たとえば、発注処理や検品、梱包、配送など、それぞれの作業にかかる時間や回数をもとにコストを配分することで、間接費をより実態に近いかたちで把握できます。従来のような「売上比率」や「数量基準」では見えにくかったコストのかかり方が明確になるため、改善策を具体的に考えやすくなります。
個別原価計算で案件ごとに収支を把握する
個別原価計算は、案件や製品ごとに原価を集計する方法です。とくに建設業や受注型の製造業、コンサルティングなどのプロジェクト型ビジネスに向いています。
案件ごとの原材料費や人件費、外注費などをすべて集計してその収支を比較することで、利益率の高い案件や改善が必要な案件を見つけられます。この手法では、進捗に応じて原価を把握することもできるため、途中で予算オーバーの兆候があれば早期に対応可能です。利益の出る案件を見極め、受注方針を見直す際にも有効なデータになります。
原価分析を経営に活かすにはどうすればいいか
原価分析の手法を知っていても、それを実際の経営にどう活用するかを考えなければ、数字は意味を持ちません。ここでは、原価分析を経営判断や業務改善に役立てるための視点や工夫について紹介します。
数字を「見える化」して現場と共有する
原価分析の結果は、経営層だけが理解していても効果は限られます。分析データをグラフやチャートにして見える化し、現場や管理職と共有することが大切です。
たとえば、材料費が急増している項目があれば、その背景を現場と一緒に考えられるようになります。情報をオープンにすることで、改善のヒントが現場から生まれることもあります。
タイムリーな分析で対応を早くする
原価分析は、月末や四半期末にまとめて行うものではありません。リアルタイムに近いタイミングで原価の動きを追うことで、素早く対策を打つことができます。
たとえば、仕入れ価格の上昇や工程の遅れが起きた場合、それが反映されたデータをもとにすぐに仕入先を見直したり、工程の再編を検討したりといった行動が可能になります。スピード感のある分析が、利益を守るうえでの大きな武器になるでしょう。
分析から得た知見を施策に落とし込む
原価分析の結果を見て終わるのではなく、次の施策につなげる視点が重要です。たとえば、ある商品やサービスの原価が高すぎるとわかったときは、仕入れ先の見直し、設計変更、販売方法の見直しなど複数の対策が考えられます。
また、利益率が高い製品に注力する方向へシフトすることで、収益構造を強化することも可能です。数字の裏にある原因を考え、行動につなげてこそ原価分析の意味があります。
部門ごとに分析の視点を変える
部署によって原価分析で注目すべきポイントは異なります。たとえば、営業部門であれば粗利率の高い商材を把握して販売戦略に活かすことが大切です。
一方で製造部門では、工程ごとの作業効率や材料ロスに注目する必要があります。経営層は、全体の収益構造の把握や投資判断の材料として活用します。
それぞれの立場に合った見方を共有することで、数字の持つ意味が具体的に活かされるのです。
分析業務を習慣化する
原価分析は一度やって終わりではなく、継続して取り組むことで効果が出ます。月次や週次で定期的に原価を確認し、過去の推移と比較する習慣をつけることで、変化に気づきやすくなります。
数字に対する感覚が社内に根づけば、問題が発生しても早く発見でき、対処も早くなります。原価分析を当たり前の業務にしていくことが、企業体質の強化にもつながります。
分析業務を支えるツールを活用する
分析に必要な情報を毎回手作業で集めていると、ミスや遅れの原因になります。複数の部門からデータを集計したり、表計算ソフトで複雑な数式を組んだりするのは時間がかかるうえ、担当者の負担も大きくなります。
そこで有効なのが、原価管理ソフトの導入です。原価管理ソフトには、入力されたデータをもとに自動で分析を行い、結果をグラフや表で表示する機能があります。リアルタイムで原価を把握できる環境があれば、経営判断のスピードと精度も大きく向上します。
まとめ
原価分析は、売上の背後にあるコストの流れを把握し、経営判断に活かすための重要な作業です。利益率の改善やコスト削減につなげるためには、数字を正しく読み取る力が欠かせません。原価差異分析やABC、個別原価計算などの手法を目的に応じて使い分ければ、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。また、数字を見える化して社内で共有すれば、部門ごとの課題や改善点も見つけやすくなります。分析業務を無理なく続けていくためには、専用ツールの活用も有効です。原価計算を楽にするために原価管理ソフトの導入もおすすめです。